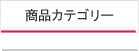
本堂 奈良時代 国宝
奈良春日山酒造株式会社(奈良市高畑町915)
奈良公園の南東、世界遺産登録の「春日山原始林」。その自然豊かな山麓、清冽な地下水が流れる名水地「清水町」で、江戸時代以前に創業の酒造業「上横田屋」を明治十年に、大阪堂島の米商であった初代 八木千之助が継承し、「真鶴」や「八木正宗」の銘柄で製造・販売していました。代表銘柄の商標「升平」は大正年間、二代目八木幸彦が、官休庵宗匠、木津宗一師より銘を受けたもので、漢書に「民有三年之儲日升平」とあります。意味として「穀物が良く実り、その価が平らかで泰平な世の中、昇平と同義で日の昇る如く栄える大平の世」と辞書に記されています。
<蔵元周辺の名所旧跡観光紹介>
新薬師寺
聖武天皇の病気を治すため薬師悔過(やくしけか)が行われ、これをきっかけに光明皇后によって春日山、高円山の麓に新薬師寺が天平19年(747)に創建されました。
悔過とは、過ちを悔いるという意味で、薬師悔過は、病苦を救う薬師如来の功徳を讃嘆し罪過を懺悔して、天下泰平万民快楽を祈る法要です。
本尊木造薬師如来坐像(国宝)とそれを囲む等身大の塑造十二神将立像(国宝)が有名です。
(参照:新薬師寺資料)
当店では二十歳未満の方には酒類を販売いたしません。
生酒商品ご購入の場合、自動的にクール料金が加算されます。
奈良・大和は日本酒発祥の地
日本酒は奈良で誕生しました。弥生時代の後期(5世紀後半西暦400年代後半)に大陸から酒造りの技術が伝わりました。
その後100~200年の時を経て日本酒独特の技法が生まれます。おそらく飛鳥時代に明日香の地で日本酒の濁酒が
完成されていたと思われます。
室町時代に、濁酒だった日本酒が澄んだお酒になります。奈良正暦寺(しょうりゃくじ)の僧侶たちが造り始めたお酒から
布で濾す習慣が生まれました。清酒の誕生です。濾して澄んだ酒は「奈良酒」と呼ばれ一世を風靡しました。
濾して出来た酒粕で奈良漬が誕生しました。奈良酒と奈良漬は全国に知れ渡ります。
奈良では脈々と続く伝統の技によって現在も美味しいお酒がたくさん育まれています。
是非一度奈良の美酒に酔いしれてください。
日本酒発祥地、奈良からお届けします!
〒636-0123
奈良県生駒郡斑鳩町興留6-2-5
もも太朗
TEL0745-75-6600 FAX0745-75-5858







